内縁の夫の死亡と財産分与、相続|最高裁平成12・3・10第一小法廷決定(最高裁平成11年(許)18号 財産分与審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件)
内縁の夫の死亡と財産分与、相続|事案の概要
女性をX、男性をAとします。
昭和22年 Aは別の女性と婚姻(その後2子Y1、Y2を授かる)
昭和29年 Aはタクシー会社を設立。
昭和46年3月 XはAと知り合い、交際を開始する。
昭和46年8月 AはXのアパートに出入りするようになり、AはXに生活費を援助するようになる。
昭和60年12月 Aは結核・肺気腫による入退院を繰り返すようになる。Xはその療養看護にあたりつづける。
昭和62年8月 Xの妻が死亡。
昭和63年11月 Aは自宅(Aとは無関係)を新築し、子Yらと新居で同居生活を開始するとともに、週のうちの何日かをX宅で過ごすという生活を送る。
平成9年1月 Aは亡くなった。
。。。。。。
Aの遺産総額は約1億8000万円で、それを子であるY2が1000万円、その余を子であるY1が相続したことを受けたそうなのですね。
現金預貯金がいくらあったのかまでは知らなかったにせよ、自宅を新築するゆとりがあり、Xの生活費も負担する経済力があったAのことを思えば、それなりの遺産があるはずだ。
Aは妻と入籍したままではあったけれど、自分との関係のほうが深くなっていたはずだ。付き合いは25年にもなるし、途中、すでに妻も亡くなっている。
Aの遺産を、ふたりの子が独占するのは、やはりおかしい。
自分にだって、遺産の一部をもらう権利はあるはずだ。
Xは、そんな思いを抱えるようになったのでしょうか。
Xは、Aの子であるY1、Y2を相手にして、Aの残した財産について、自分への分与を求めて、家庭裁判所に審判を申立ました。
内縁の夫の死亡と財産分与、相続|財産分与か相続か
ところで、いわゆる法律婚(婚姻届提出済み)の場合、夫が亡くなれば、妻は、夫の財産(遺産)を相続することができます(民法890条。配偶者の相続権)。
では、内縁の場合(婚姻届の提出を欠くが、実態は夫婦同様の生活を送ってきている)は、どのように考えるべきでしょうか。
内縁の妻であるXは、内縁の夫であるAが亡くなったとき、Aの残した財産について、何らかの請求をすることができるのでしょうか。
内縁のケースについて、直接規定している条文がないため、問題となります。
考え方のひとつとして、
配偶者の相続権を定めた民法890条が、内縁のケースにおいても、準用されるという考え方がありえます。
もうひとつの考え方として、
離婚の際の財産分与を定めた民法768条が、内縁の解消のケースにおいても、準用されるという考え方がありえます。
一般論として、内縁の場合に、残されたパートナーの相続権を認める(民法890条)判例や学説は見当たらないようです。
そのため、本件の女性Xも、民法890条(配偶者の相続権)の準用を主張するという作戦はとらなかったようです。
Xは、Aが、生前、Xに対して財産分与義務(民法768条)を負っていたはずであり、Xの子であるY1、Y2がそれを相続したとして、
Y1、Y2に対し、財産分与を求める審判を申し立てたのです。
内縁の夫の死亡と財産分与、相続|裁判所の判断
Xからの申し立てに対し、Y1、Y2は、そもそもXとAとは、いわゆる内縁の関係にはない(法的には無関係の人物にすぎない)と主張して、Xの請求を争いました。
原原審(高松家裁)は、XとAとの関係が、内縁の関係にあることを認めたうえで、過去の扶養的要素部分に関する財産分与として、Y1、Y2に対し、あわせて1000万円の支払を命じました(清算的要素部分についてはすでに十分な贈与を受けていたことを理由に請求を退けた)。
Xとしては、遺産全体からすると少額に感じたかもしれませんが、少しは気が済むところもあったでしょう。
しかし、子らからすると、1000万円であっても耐え難い支払に感じたのかもしれません。
なぜ、母でもなんでもない「無関係」の人物に父の遺産を奪われなければならないのかと。
Y1、Y2は、抗告しました。
原審(高松高裁)は、Y1、Y2の抗告を容れて、原原審の審判を取り消して、Xの申立てを却下しました。
Xとしてはショックだったでしょうね。まさかゼロにまで戻ってしまうとはと。。
Xは最高裁に許可抗告の申し立てをしました。
内縁の夫の死亡と財産分与、相続|最高裁判所の判断
最高裁判所は、次のように述べて、Xの抗告を棄却しました。
《内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法768条の規定を類推適用することはできないと解するのが相当である》
《民法は、法律上の夫婦の婚姻解消時における財産関係の清算及び婚姻解消後の扶養については、離婚による解消と当事者の一方の死亡による解消とを区別し、前者の場合には財産分与の方法を用意し、後者の場合には相続により財産を承継させることでこれを処理するものとしている》
《このことにかんがみると、内縁の夫婦において、離別による内縁解消の場合に民法の財産分与の規定を類推適用することは、準婚的法律関係の保護に適するものとして合理性を承認し得るとしても、死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産清算の道を開くことは、相続に寄る財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので法の予定するところである》
《また、死亡した内縁配偶者の扶養義務が遺産の負担となってその相続人に承継されると解する余地もない》
《したがって、生存内縁配偶者が死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有するものと解することはできないと言わざるを得ない》
結局、最高裁は、
内縁の場合は、法律婚と違って、パートナーが亡くなったからといって、その財産を相続することはできないし(民法890条の準用、類推適用はない)、理屈をつけて財産分与を求めることもできない(民法768条の準用、類推適用もない)。但し、離婚と同じように、生前に別れる場合は(内縁関係の解消)は、財産分与(民法768条)の規定を類推適用して、その財産分与の要求をすることができる。
としたのです。
内縁の夫の死亡と財産分与、相続|内妻として、どうしておけばよかったのか
これはもう、タラレバになってしまいますし、実際にお願いしたけど叶わなかったのかもしれませんが、Xは、Aと入籍しておくべきでした。
そうすれば、法定相続分の2分の1相当は自分のものにすることができた。
あるいは、入籍まではいかずとも、AはXに対し、生前財産の全部又は一部を自分に遺贈するという、遺言を残しておいてもらうべきでした。
そうすれば、財産のうちいくらかは取得することができた。
少なくとも、ゼロ、ということはなかった。
実際には、AにはAなりの思い(子への感謝や、遺産についてはすべて子が取得すればいいという考えなど)があったのかもしれませんが、あとで揉める可能性を少しでも感じていたのであれば、少しでもいいからXへの遺贈を認める遺言を残しておいてあげれば、Xが、Aの子らと裁判をするような事態は避けられたのではないでしょうか。
もっとも、Aからすれば、そこまでの未来は予測できなかった、Aからみて、Xは、人の財産のことに口をだすような女性ではない、などという思いがあったのかもしれません。
事後的に、私のような部外者がやいのやいの言うのは楽ですが、実際の判断は、なかなかに、難しい。
それでもやはり。
私はAがXと入籍はしないとしても、遺言はのこしてあげればよかったと思います。
想像絡みの紛争は、遺言さえあればここまでもめずに済んだだろうな、という事案が珍しくないのです。
本事例も、その一例といえますね。
内縁の夫の死亡と財産分与、相続|余談として
私は、この判例は、たいへん面白い判例だと思っています。
なぜか。
内縁の夫婦の離別(法律婚であれば離婚)にも、財産分与を認めてあげるのであれば、
内縁夫婦の死別(法律婚であれば相続の場面)にも、相続を認めてあげればよい。
そう思いませんか?
これをこの最高裁判例は、財産分与は認めるのは、内縁という準婚的法律関係の保護に適するといいながら、相続を認めるのは、法の予定しないところなどといって、相続を認めないのです。
準婚的法律関係の保護の必要性を論じるのであれば、離別(財産分与)の場面であろうが、死別(相続)の場面であれば、等しく保護されるべきというのが、むしろ論理一貫するのではありませんか。
だって、内縁とは、婚姻届こそ提出はないが、実際には夫婦の実態があると評価されるもので、だからこそ、法律婚の夫婦と同様の保護を与える形で、民法を解釈して、夫婦と同じような法適用をするように処理してきたのが裁判実務なのですから。
ここで、法の予定しないところなどという理屈を持ち出すのであれば、婚姻届を提出しない夫婦(内縁関係)に財産分与の規定を適用させるのは、法の予定しないところだ、と言おうとすれば言えてしまうのではありませんか。
つまり、最高裁のこの判決文も、全く一貫していないのです。
論理もなにもない、要は、裁判とは、裁判官の価値判断を示す儀式である(ことがかなり多い)ことを教えてくれる、良いサンプルです。
私としては、裁判批判をしたいのではなくて、裁判とはそういうものということを皆さんに知っていただきたいのですね。
ケースバイケースで、もっともらしく(ある意味、適当な言葉で)、裁判所がもっていきたい結論に至る理屈(時に、屁理屈。時に、理屈にすらなっていない、単なる価値判断)を書き連ねて、もっていきたい結論を宣言する。
裁判とは、このようなものであるからこそ、逆に、どんなケースであっても、自らの主張を徹底的に、妥協することなく、訴えていくことが必要となりますし、そこで果たされる弁護士の役割、期待される力量(裁判所を説得する、事実経過の整理、情報の整理、取捨選択、訴求力ある理屈、結論、価値判断、文章表現等々の能力)も大きいといえるのです。
とにかく、この判例から学んでおくべきことを、
最後にもう一度念押ししておきますと、
「内縁は離別(離婚と同じ)のときは、財産分与を請求できる」
「内縁は死別のときに、遺産がもらえない」(但し、将来の判例変更があれば別。)
これは現代国民必須の法律知識としておきましょう。
最高裁平成12・3・10第一小法廷決定
(最高裁平成11年(許)18号 財産分与審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件)
(民集54巻3号1040頁、判例時報1716号60頁、判例タイムズ1037号107頁)
 新宿 弁護士 うみとそら法律事務所の相続相談室
新宿 弁護士 うみとそら法律事務所の相続相談室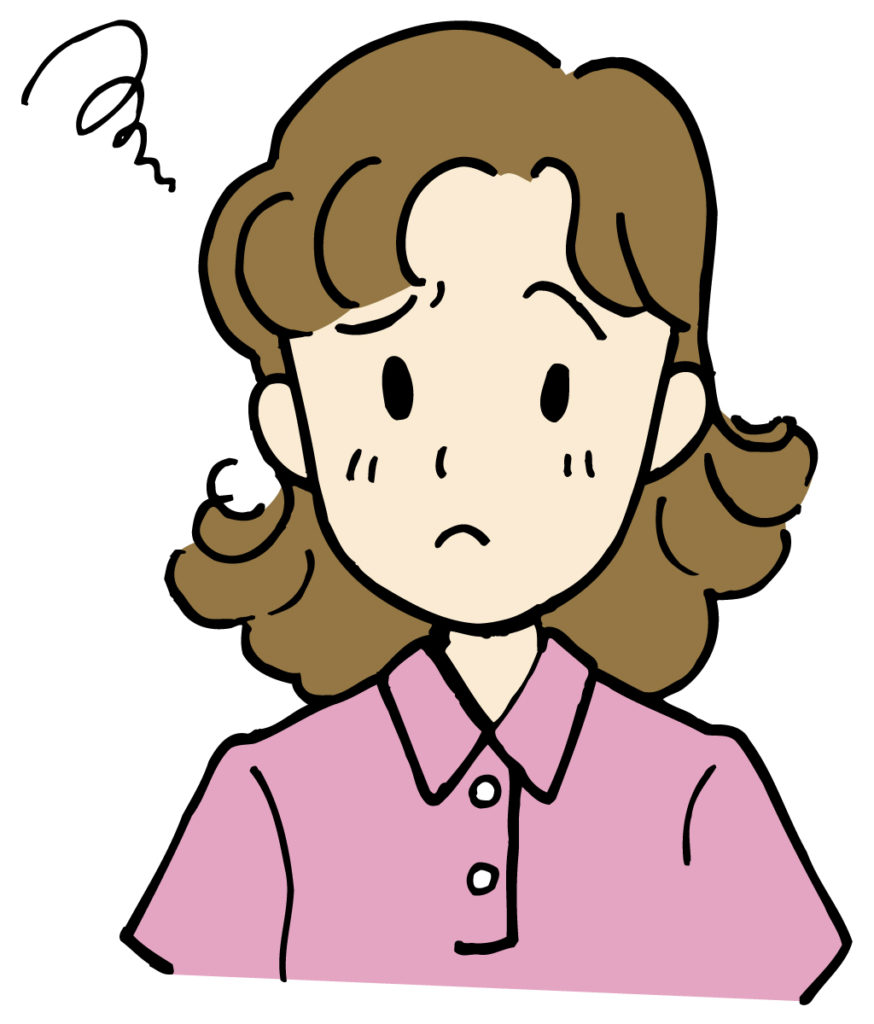


コメントを残す